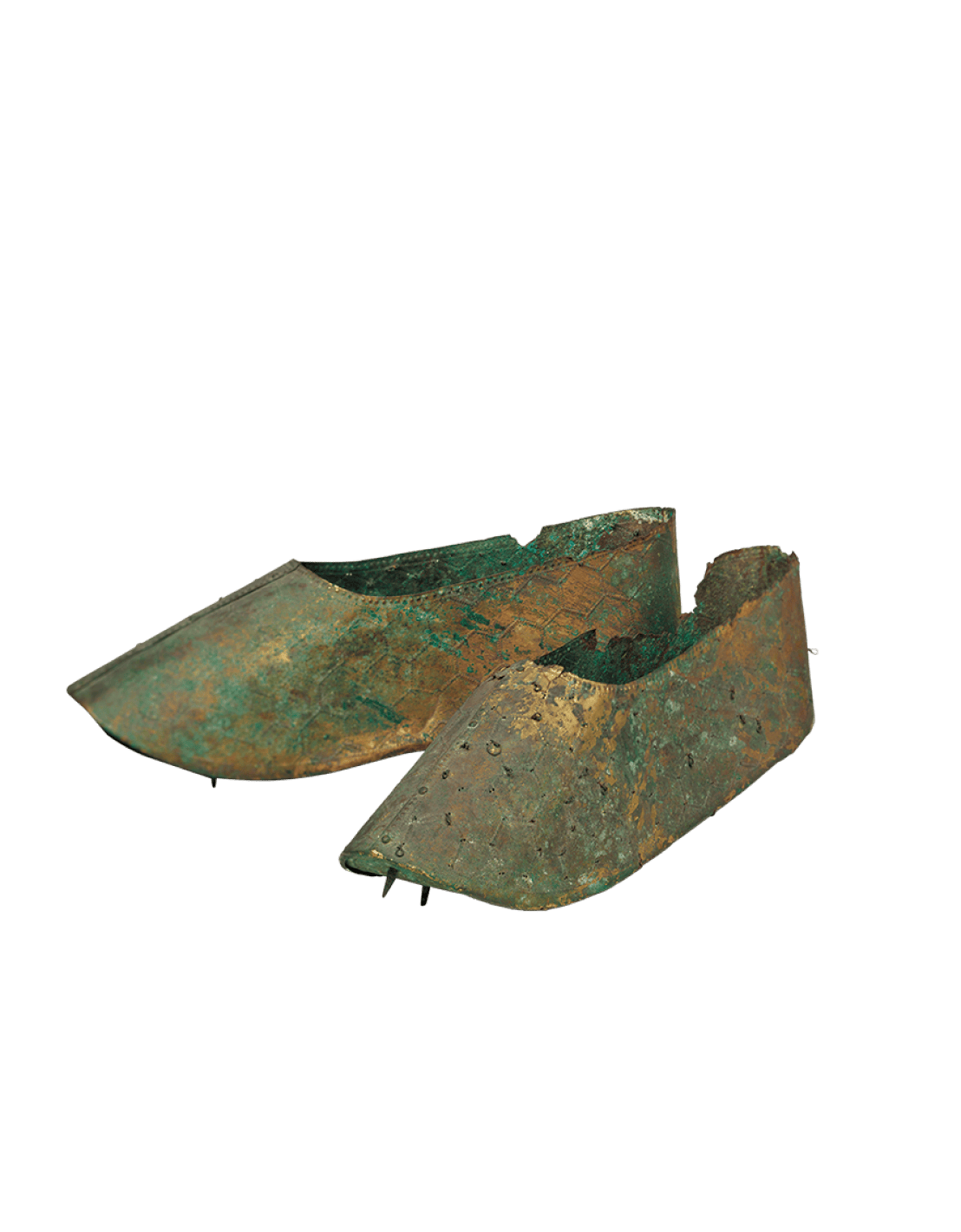国宝 金象嵌銘大刀
奈良県天理市 東大寺山古墳出土
古墳時代・4世紀〔刀身:中国 後漢時代・2世紀〕
東京国立博物館蔵
中国の後漢王朝で2世紀に作られた大刀で、銘文には後漢の年号「中平」(184~189年)が入っています。当時、「倭国大乱」とも表現された戦乱の日本列島に贈られた大刀は、200年間保管され、日本製の花形環頭柄頭がつけられて東大寺山古墳に納められました。